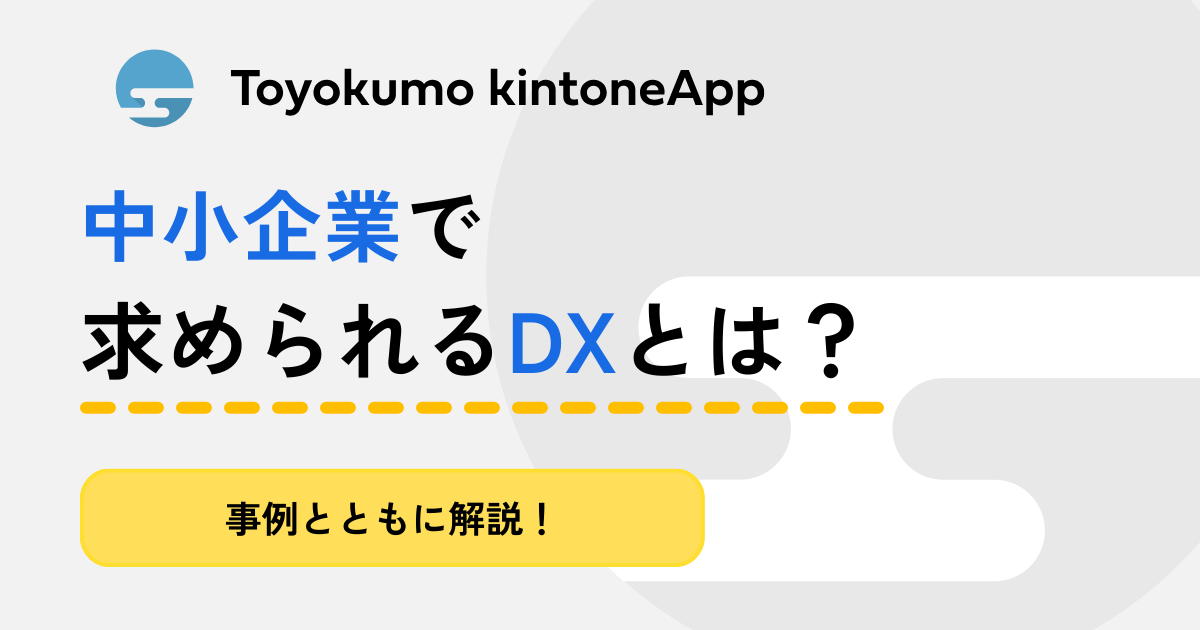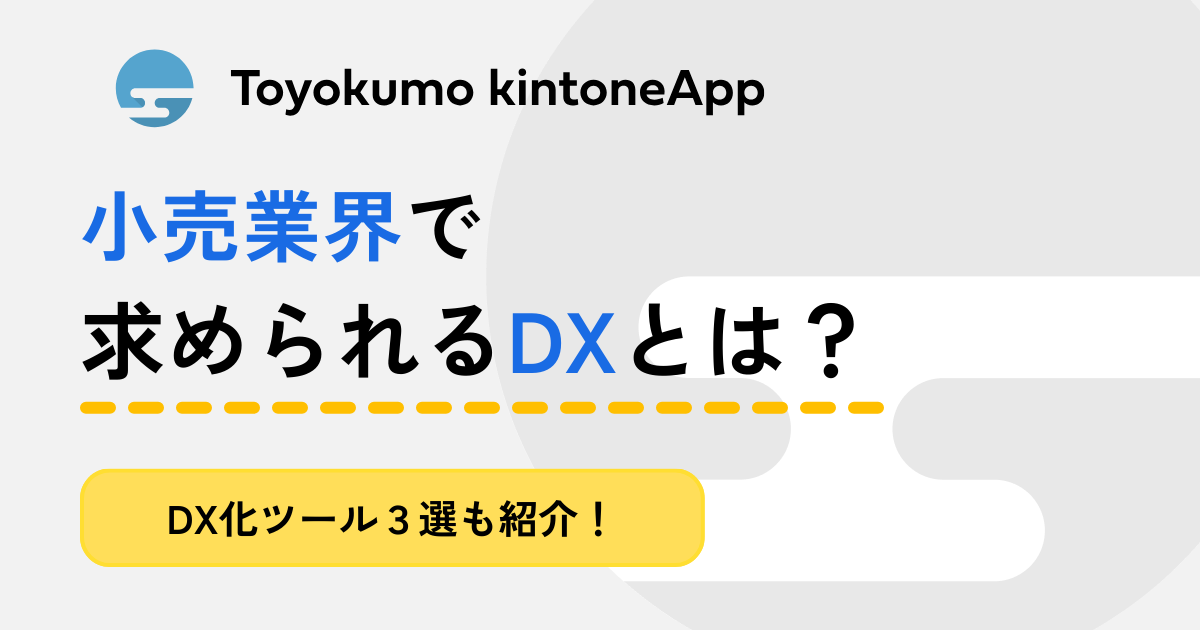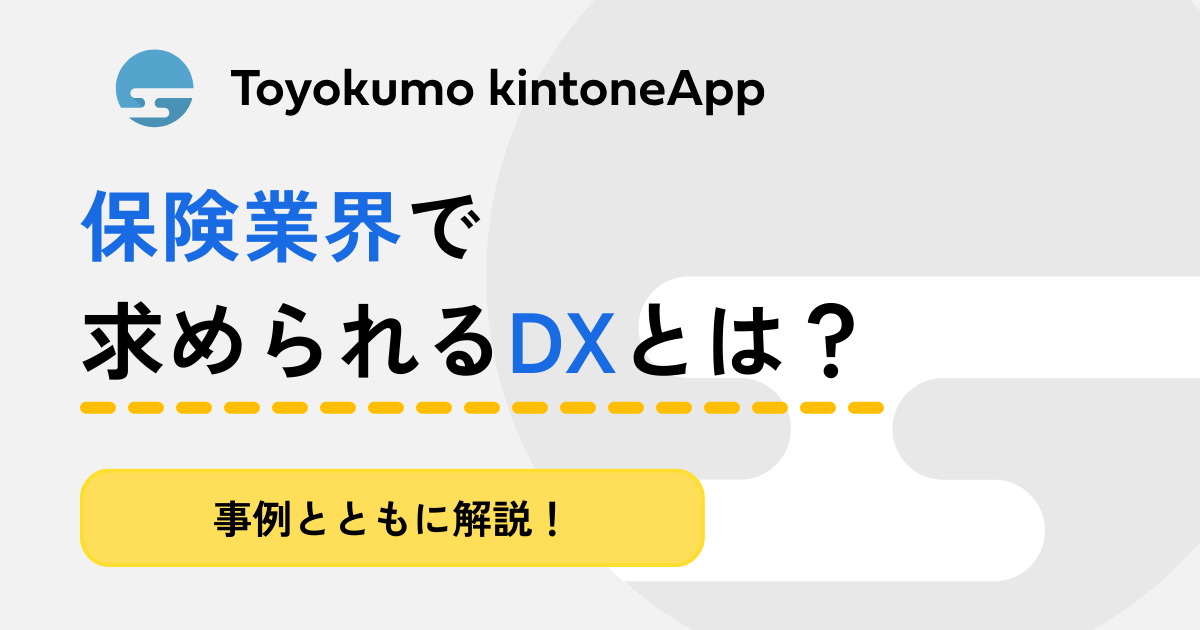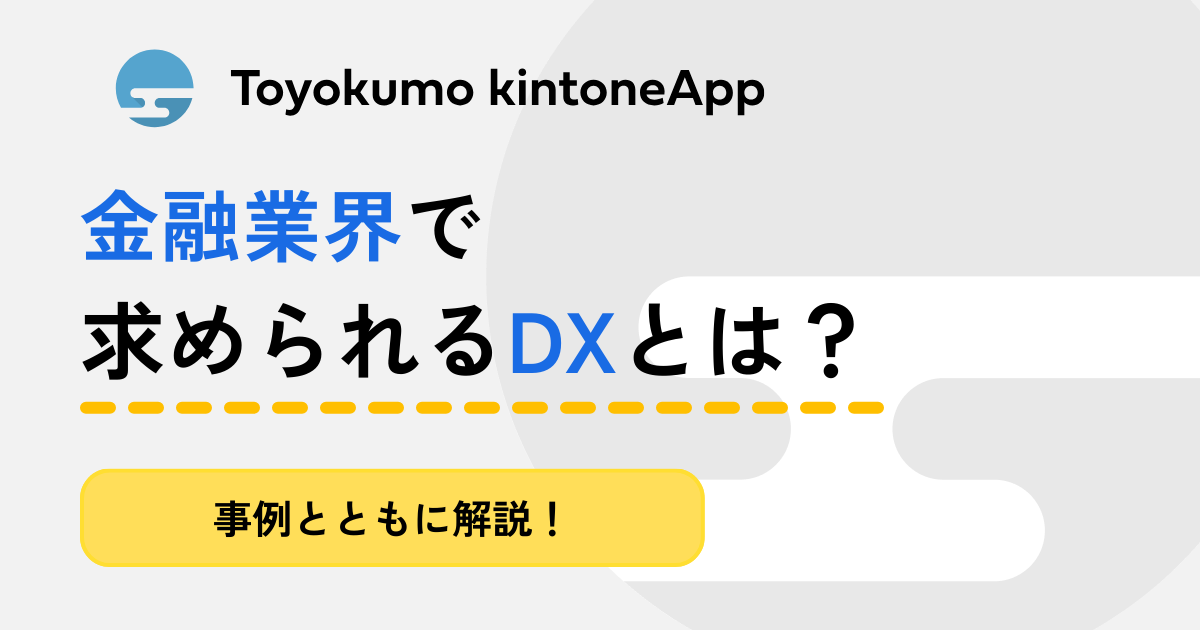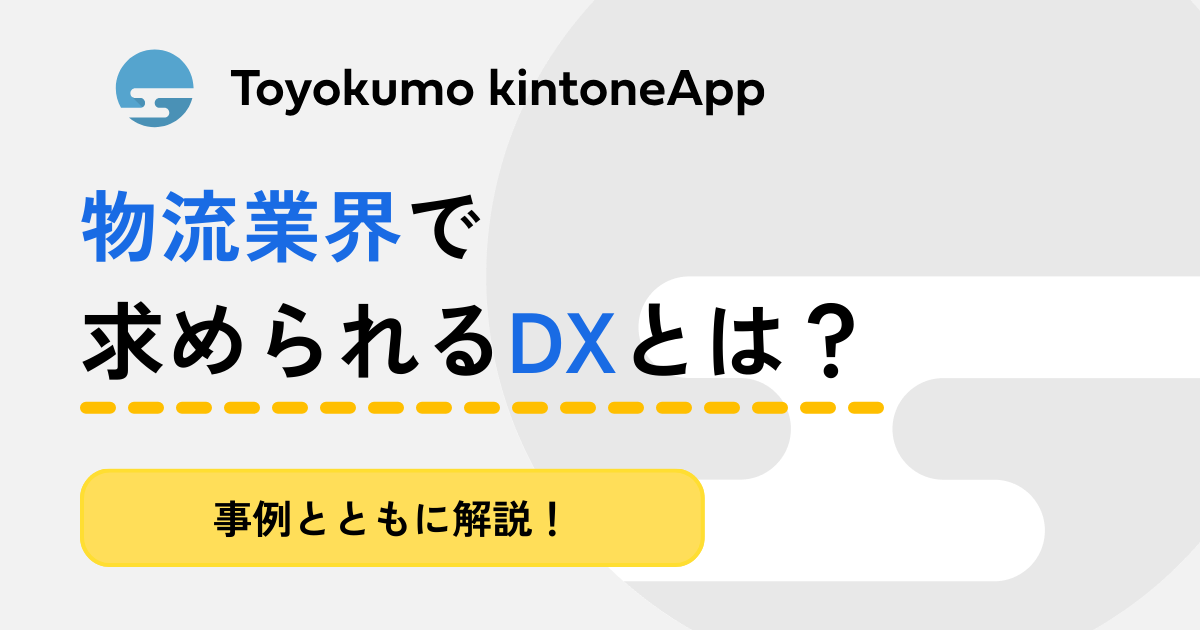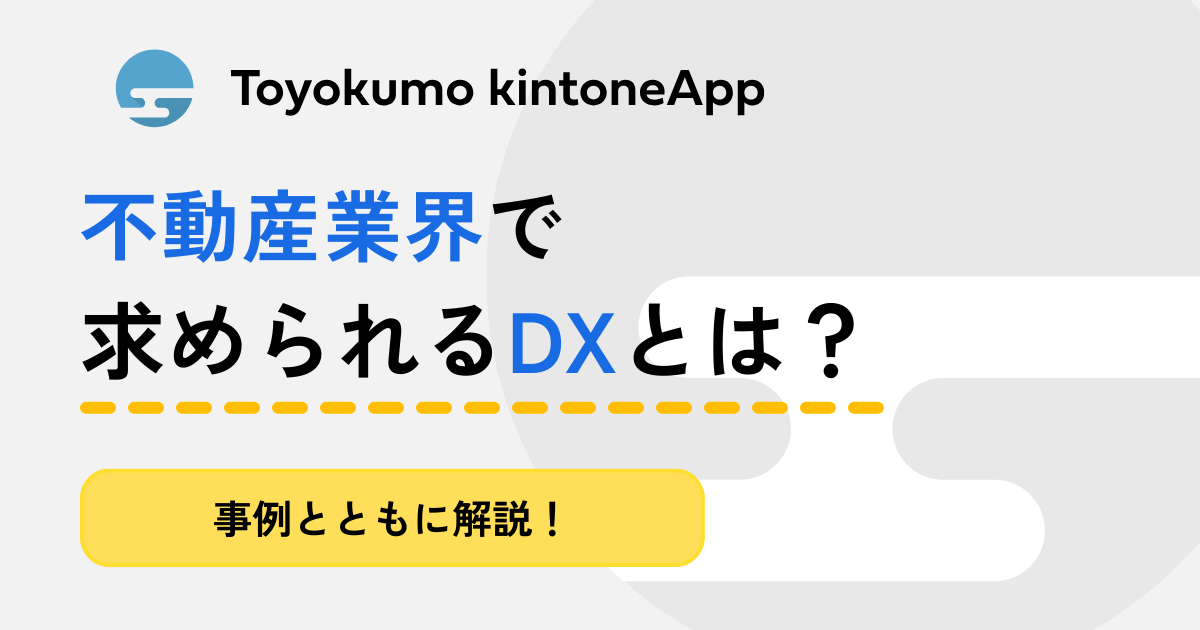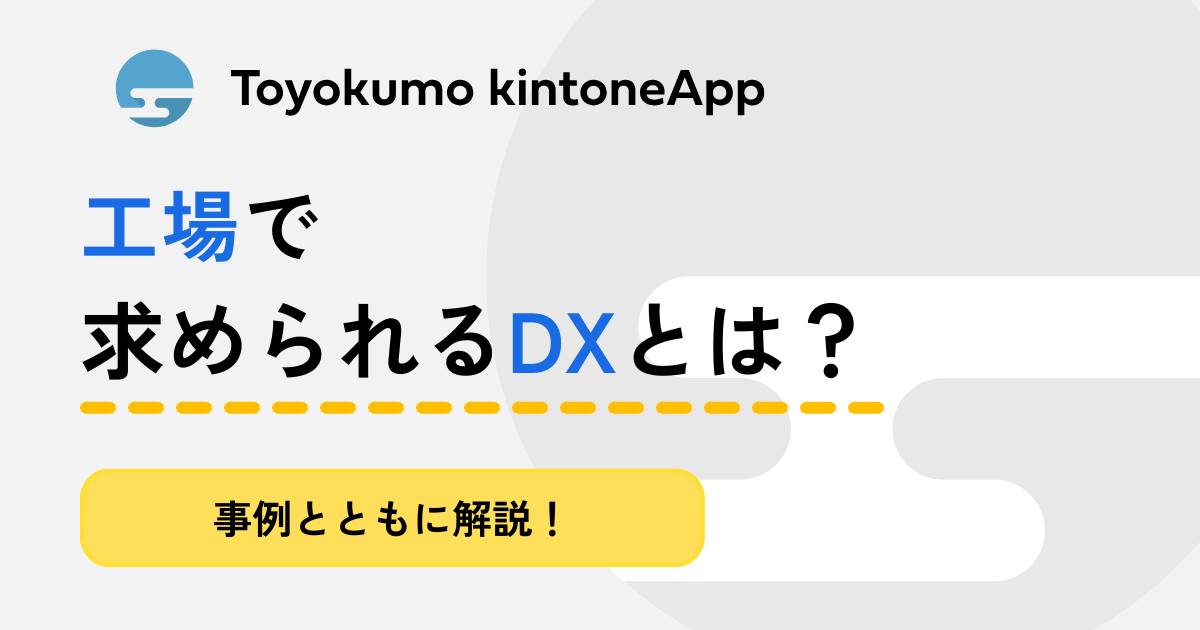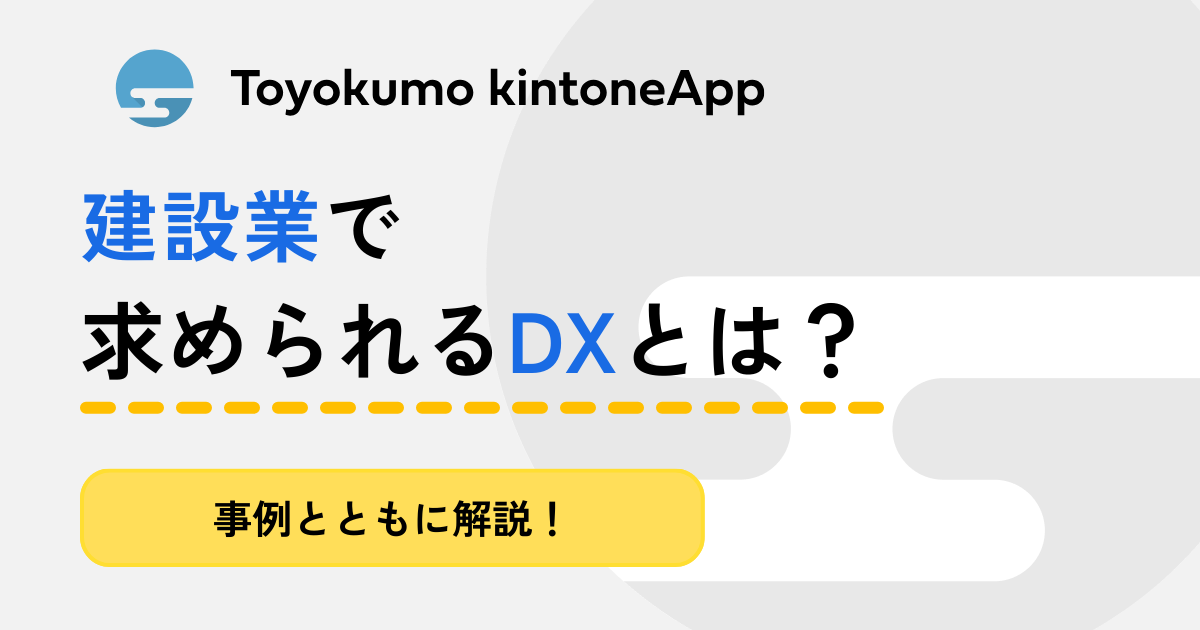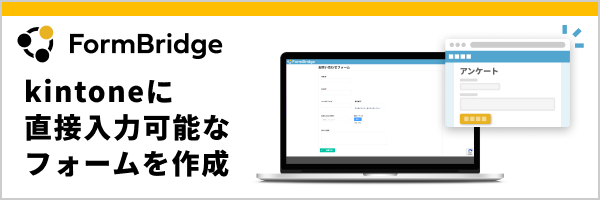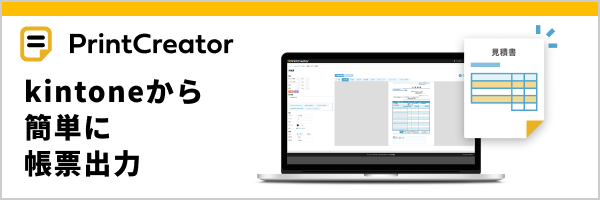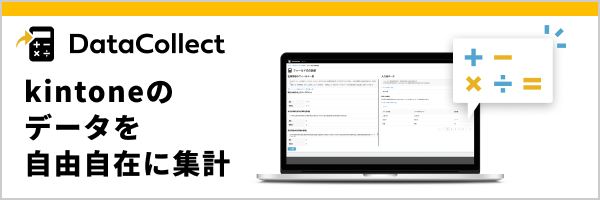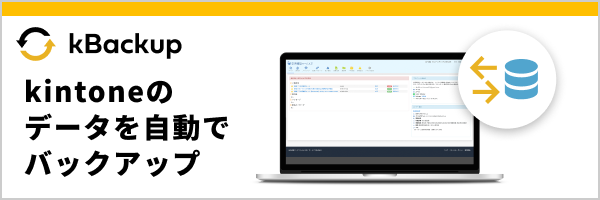【事例あり】医療DXとは?求められている背景や推進時の課題・取り組み事例を紹介
医療業界で進むDXは、医療サービスの質向上や効率化、そして患者様の利便性向上を目指す大きな変革です。
医療DXは、医療従事者の負担軽減や地域医療の強化にも寄与すると期待されています。
しかし、DXを推進するには、技術面や制度面での課題も多く存在します。
本記事では、医療DX推進における課題、そして具体的な取り組み事例を通じて、その重要性と意義について解説します。
目次
医療業界における3つの問題
医療業界では、主に以下3つの問題が顕著になっています。
- 最新の医療事案に関するデータ収集の遅れ
- 2024年問題
- 人手不足
これらの問題は、医療提供の質や迅速性に影響を及ぼしており、効率的な解決策が必要です。
最新の医療事案に関するデータ収集の遅れ
医療現場では、患者様の症状、検査結果、治療履歴といった情報が、疾病の傾向把握や最適な治療法の選択に役立つため、データの収集が重要視されています。
しかし、現在の医療システムでは、最新の医療データ収集が追いついていない場合もあり、診断の精度低下や治療の遅れを招くケースもあります。
厚生労働省が発表した「医療DXについて」という資料でも、データ収集や共有体制の課題が挙げられており、リアルタイムでの情報取得や分析が求められている現状です。
その解決策として、医療DXを進めることで迅速にデータを活用できるようになれば、より正確な診断やスピーディーな治療が実現可能になるでしょう。
2024年問題
「2024年問題」とは、医療従事者の働き方改革によって、医療現場に与える影響を指します。
特に、労働時間に上限規制が設けられるため、既存の人員体制や業務フローの見直しが急務です。
しかし、人の生命に関わる医療では、労働時間が減ってもサービスの質を落としてはいけず、人々からの需要が低くなることは考えにくい状況です。
そこで、DXを推進し、サービスの質を落とさずに効率的な業務管理がを実現することが期待されています。
人手不足
医療業界では深刻な人手不足が問題となっており、特に介護や看護分野での負担が大きいのが現状です。
厚生労働省が発表した「令和4年版 厚生労働白書」によれば、高齢化などで医療・福祉サービスを必要とする方々の増加が理由の一つと考えられています。同時に、少子化によって労働人口は減少傾向にあるため、デジタルツール導入による業務効率化などで人手不足の緩和を図る取り組みが進められています。
DXによる業務の省力化や支援技術の導入は、少ない人材で質の高い医療を提供するために必要不可欠な取り組みだと言えるでしょう。
医療業界で実践するDXの例2選
現場では、電子処方箋や予防接種のオンライン申込といったデジタル技術の活用が進んでいます。
これらの取り組みは、業務効率化や患者様の利便性向上を目的とし、DXの一環として導入が加速している状況です。
具体的な取り組み事例から、医療DXがもたらすメリットや効果を紹介します。
電子処方箋
電子処方箋は、医療の質向上を目指して行われている取り組みの一つです。
電子処方箋を導入することで、医療機関と薬局間の情報共有を効率化し、患者様の待ち時間短縮に繋がります。
さらに、薬剤情報の一元管理が進むことで、重複投薬チェックなど安全かつ迅速な処方管理が可能です。
電子処方箋は、全国規模での情報共有基盤の整備にも役立ち、処方データの分析による医療費の削減も見込まれています。
予防接種のオンライン申込
予防接種のオンライン申し込みシステムは、患者様と医療機関の連携を円滑にし、手続きの簡素化を可能にします。
オンラインでの申請により、待ち時間の短縮や誤解のリスクが減り、患者様と医療従事者双方の負担軽減に繋げることが可能です。
また、デジタルでの予約や記録管理になるため、感染症対策や予防接種の受診率向上も見込まれます。
医療業界でのDX取り組み事例3選
DXを積極的に推進している企業や団体は、業務効率化や医療の質向上に大きな成果をあげています。
ここでは、以下の3つの事例を通して、医療業界でどのようにDXが導入され、効果を発揮しているかを紹介します。
- 中外製薬株式会社
- 第一三共株式会社
- 横浜市医師会
中外製薬株式会社
 参照:デジタルトランスフォーメーション “CHUGAI DIGITAL”|中外製薬株式会社
参照:デジタルトランスフォーメーション “CHUGAI DIGITAL”|中外製薬株式会社
中外製薬株式会社では、「世界最高水準の創薬の実現」と「先進的事業モデルの構築」の目標を実現するために、DXを推進しています。
具体的には、AIやデータサイエンスを活用して創薬プロセスを効率化し、より迅速な薬剤開発を推進。こうした取り組みにより、患者様に新しい治療法を届けるスピードを加速させることが期待されています。
さらに、革新的な製薬技術や臨床データを活用し、がんなどの難治性疾患の治療法開発にも注力しています。
第一三共株式会社
 参照:DX – データと先進デジタル技術の活用|第一三共株式会社
参照:DX – データと先進デジタル技術の活用|第一三共株式会社
第一三共株式会社は、デジタル技術を活用して医療データの管理・分析を行い、顧客価値の最大化を目指しています。
同社では、統計解析やエンジニアリングサポートといったあらゆる技術を活用し、患者様一人ひとりに寄り添った医療の実現に向けてDXを積極的に推進。医療機関への迅速な情報提供や、医薬品の新たな効果の探索などを実現する基板整備に取り組んでいます。
こうしたDXにより、新たな医療サービスを作り出すと同時に、安全かつ効果的な医薬品の研究開発に努めています。
一般社団法人 横浜市医師会
 参照:コロナワクチン接種管理システムを、たった1か月で構築から運用まで実現した活用法とは|Toyokumo kintoneApp
参照:コロナワクチン接種管理システムを、たった1か月で構築から運用まで実現した活用法とは|Toyokumo kintoneApp
横浜市医師会では、業務効率化を目的にkintoneとトヨクモkintone連携サービスを導入し、業務プロセスのデジタル化に取り組んでいます。
同社では、ワクチン予約の登録・確認やアンケート収集などを統一のプラットフォームで管理するフローへ変更。出勤日時や接種会場といったシフト関連の情報が見える化され、看護師の業務負担が軽減されています。
業務効率化を進め医療従事者が働きやすい環境をつくることで、市民が安心して利用できる地域医療の基盤としての役割も果たしています。
医療DXを進める上での2つの課題
医療DX推進に伴い、セキュリティ対策やスタッフ・患者様への教育が重要な課題として挙げられます。
こうした課題にどう対処すべきか事前に把握し、医療DXの効果を最大限発揮しましょう。
セキュリティ対策
医療業界では、サイバーセキュリティの強化が必須です。
患者様の個人情報、特に病歴や健康診断といった情報は、他の情報よりも厳格な管理が求められるため、データの暗号化やアクセス権の管理が重要となっています。
また、DX推進に伴ってネットワーク経路が拡大したことでサイバーリスクも増しているため、専門的な対策が急務です。
さらに、サイバー攻撃の未然防止に向けたトレーニングや、迅速な復旧体制の構築も重要視されています。
スタッフや患者様への教育
DX推進では、医療従事者や患者様が新しいシステムに適応するための教育が不可欠です。
しかし、ITリテラシーの低い医療従事者や患者様は、どの現場にも一定数いるのが現状です。
そのため、デジタルツールの使い方やリテラシー向上を図り、現場でのスムーズな運用が求められています。
教育により利用者の理解が深まれば、DX活用による業務改善や患者様満足度の向上も期待できるでしょう。
医療DXに役立つ業務改善ツール3選
医療業界での業務改善には、デジタルツールの活用が大きな役割を果たしています。
ここでは、以下の3つの業務改善ツールを取り上げ、医療現場でのDX支援にどう貢献しているかを解説します。
- PigeonCloud
- JUST.DB
- kintone
PigeonCloud
PigeonCloudは、医療現場における訪問管理や業務効率化を支援するクラウド型システムです。
スケジュール管理やスタッフの配置、実績記録などを一元的に管理します。
スマートフォンやタブレットからも利用可能で、訪問先でのデータ確認が簡単に行えるため、情報共有の迅速化とペーパーレス化が可能です。
加えて、リアルタイムでのデータ更新も可能で、迅速な意思決定をサポートします。
業務効率化と同時に、サービスの質向上にも寄与し、医療のデジタル化を支えるツールとして注目されています。
JUST.DB
JUST.DBは、医療現場でのデータ管理を効率化するデータベースツールです。
医療DXの推進において、JUST.DBは診療データや患者様情報などの膨大なデータを一元的に管理し、迅速な情報共有を可能にします。
簡単に導入できる上に、医療現場に合わせて柔軟にカスタマイズが可能で、操作性の高さも特徴です。
電子カルテや各種データベースと連携することで、医療スタッフの業務効率が向上し、患者様対応にも迅速に対処できるようになります。
kintone
kintoneは、医療現場での情報共有と業務管理を効率化するクラウド型データベースツールです。
医療DXの一環として、kintoneは患者様情報や業務データを一元管理し、各種書類や業務フローを可視化します。
簡単な操作でカスタマイズができるため、医療機関のニーズに応じた運用が可能です。
例えば、医師や看護師の間でのスムーズな情報共有や、タスクの進行管理を効率化し、医療従事者の負担を軽減します。
医療の質向上に寄与する重要なツールとして多くの場所で活用されています。
医療業界でkintoneがどのように活用されているか、詳しくは下記からご確認ください。
kintoneをより便利に使うならToyokumo kintoneApp
 kintoneをより便利に使うためにおすすめしたいのが、トヨクモ株式会社が提供するkintone連携サービス「Toyokumo kintoneApp」です。
kintoneをより便利に使うためにおすすめしたいのが、トヨクモ株式会社が提供するkintone連携サービス「Toyokumo kintoneApp」です。
Toyokumo kintoneAppでは、以下6つのサービスが提供されています。
| FormBridge | kintoneへデータが自動で保存されていくWebフォームを作成できるサービス |
| PrintCreator | kintoneアプリのデータをPDFで出力できるサービス |
| kViewer | kintoneライセンスがない人に、kintoneアプリのデータを共有できるサービス |
| kMailer | kintoneアプリのデータを引用してメール送信できるサービス |
| DataCollect | 複数のkintoneアプリに登録されたデータを集計できるサービス |
| kBackup | kintoneアプリに登録されたデータを安全にバックアップするサービス |
ここからは、Toyokumo kintoneAppの各サービスについて紹介します。
FormBridge
FormBridge(フォームブリッジ)は、kintoneアカウントがない人でもkintoneに直接データを保存できるWebフォーム作成サービスです。
kintoneの基本機能における「ライセンスを持たないユーザーは情報を登録できない」という問題を解消できます。
また、FormBridgeで作成したフォームは、kintoneに直接データが保存されるため、転記の必要がなく、業務効率化や入力ミス・漏れの削減ができるのがメリットです。
kViewer
kViewer(ケイビューワー)は、kintone内の情報を手間なく外部に公開できる連携サービスです。kintoneアカウントを持たないユーザーにも簡単にkintone内の情報を公開できます。
kintoneの情報を共有する際にわざわざデータを移し替える手間もなく、グラフなどの数値情報もそのまま外部に公開することが可能です。
公開範囲を設定することもできるので、社外秘の情報が漏洩するリスクを抑えつつ、社外の人に資料やデータを気軽に共有できるようになります。
また、FormBridgeとkViewerでは、「マイナンバーカードで本人確認」のオプションを提供開始しました。デジタル庁が提供する「デジタル認証アプリ」を利用することで、行政手続きでの給付対応や各種予約といった手続きの際、簡単に本人確認を実施可能です。本機能の詳細な仕様や利用方法については、下記ページをご覧ください。
kMailer
kMailer(ケイメーラー)は、kintone上で管理しているメールアドレス宛に、kintone内のデータを自動引用したメールを自動・手動・予約で送れるサービスです。
kintoneで管理している顧客に向けて一斉送信や、kintoneからのテキスト引用などを行ったり、誰にいつどんなメールを送信したかなどのログを確認することもできます。
普段社内で使っているメールアドレスからメールを送信するため、新たにメールサーバーやメールアドレスを用意する必要はありません。
誰に、いつ、どんなメールを送信したか、受信者がいつ資料をダウンロードしたかなどの情報をログとして確認することもできます。
PrintCreator
PrintCreator(プリントクリエイター)は、kintoneに登録されている社名や金額などの情報を活用して、マウスのみで簡単に帳票が作成できる帳票出力サービスです。
現在使用している見積書や請求書などをPDFファイルでPrintCreatorにアップロードすれば、マウス操作のみで簡単に帳票を作成できます。
kintoneアプリの複数レコードを一括で出力できるので、複数社の請求書や月報を簡単に印刷できるのもメリットです。
DataCollect
DataCollectk(データコレクト)は、関数を利用した計算や複数アプリ間の収集・計算・加工を可能にし、kintoneが苦手とする予実管理や在庫引き当てを実現できるサービスです。
Excelと同じ感覚で複数のアプリから情報の集計や計算が可能で、スケジュール設定による自動実行やリアルタイム更新などにも対応しています。
事前に設定しておけば、手動で操作することなく情報を自動で収集・計算できるので、情報の集計漏れや更新忘れを防げます。
kBackup
kBackupk(ケイバックアップ)は、kintoneアプリに登録したデータが消えてしまった際に備えて、kintone内のデータを別環境にバックアップできるサービスです。
kintoneの基本機能では、kintone上のすべてのデータを一括でバックアップすることはできません。kBackupを利用することで、誤って必要なアプリを削除してしまったり、スペースが復旧できなくなったという事態を防げます。
また、大切な顧客情報や添付ファイルのバックアップにも対応しています。
まとめ:Toyokumo kintoneAppでkintoneをより便利に活用しよう
 「kintoneで貸出管理を行いたい」「kintoneを活用する幅を増やしたい」とお考えの方は、kintone連携サービス「Toyokumo kintoneApp」の利用がおすすめです。
「kintoneで貸出管理を行いたい」「kintoneを活用する幅を増やしたい」とお考えの方は、kintone連携サービス「Toyokumo kintoneApp」の利用がおすすめです。
トヨクモのkintone連携サービスは1万契約を突破し、サイボウズのオフィシャルパートナー評価制度においても全製品で受賞と、実績と使いやすさに定評があります。
トヨクモ連携サービスを導入することで、紙の書類を介さず、直接データの書き込みや管理が行えるため、職員の負担軽減や業務効率改善が図れるでしょう。
| FormBridge | kintoneへデータが自動で保存されていくWebフォームを作成できるサービス |
| PrintCreator | kintoneアプリのデータをPDFで出力できるサービス |
| kViewer | kintoneライセンスがない人に、kintoneアプリのデータを共有できるサービス |
| kMailer | kintoneアプリのデータを引用してメール送信できるサービス |
| DataCollect | 複数のkintoneアプリに登録されたデータを集計できるサービス |
| kBackup | kintoneアプリに登録されたデータを安全にバックアップするサービス |
悩みややりたいことに合わせて最適な機能を追加できるので、kintoneと一緒に使いたい便利なサービスをお探しの場合は、30日間無料お試しからぜひ実際の使用感を体感した上でご検討ください。
なしYamadaNaoki