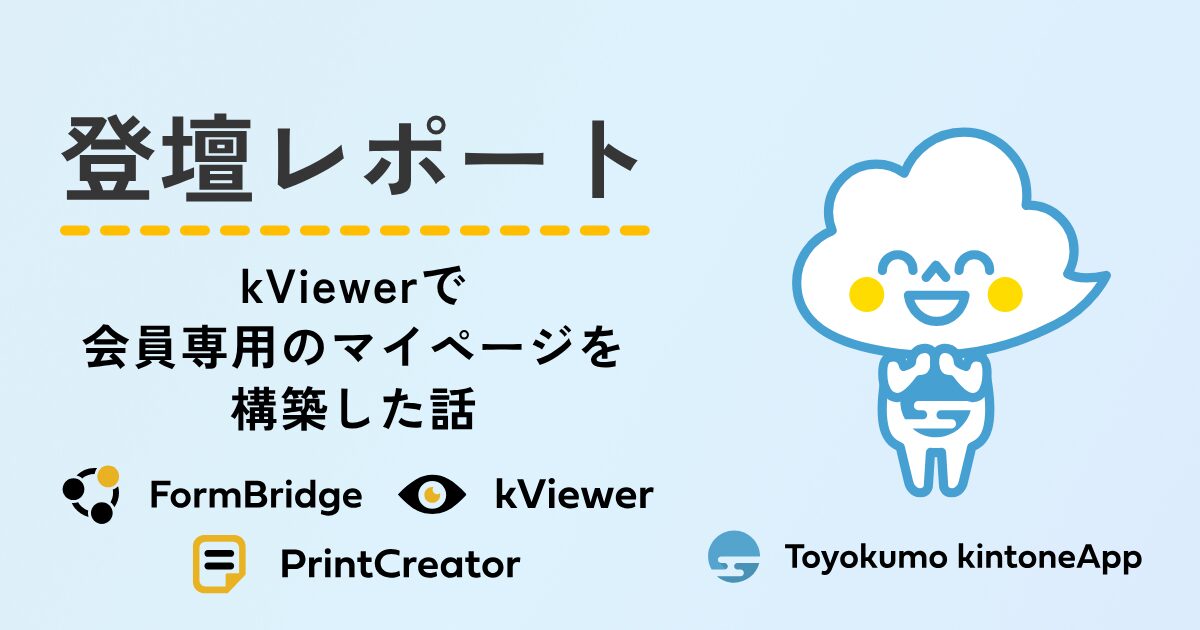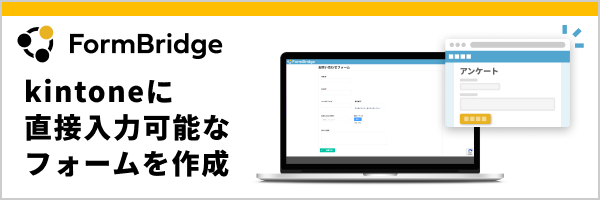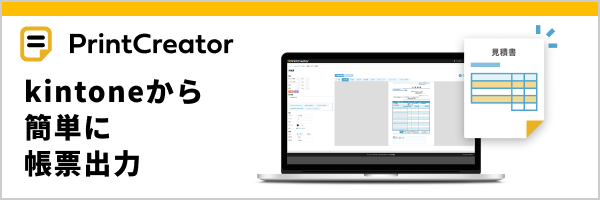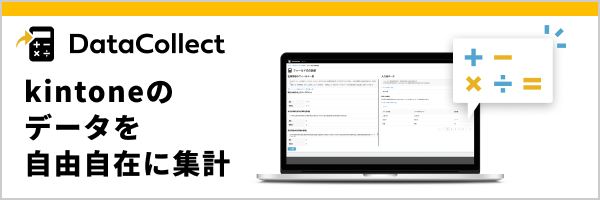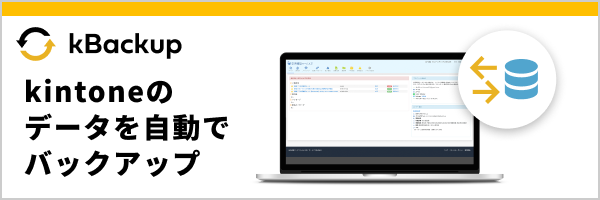【2024年トヨクモkintone収穫祭アフターイベント】 お悩み相談パネルセッションレポート記事

この記事はトヨクモkintone収穫祭のアフターイベントで行われたトークセッションの様子をお届けするレポート記事です。
今回は、株式会社SBI証券 吉田敬史氏、株式会社成田デンタル 吉原大騎氏のお二人にご登壇いただき、参加者の皆さまから頂戴した質問にお答えいただきました。
なるべく当日の空気感をそのままお伝えできるよう、お話しいただいた内容をできるだけそのまま掲載しています。

目次
自己紹介
トヨクモ:こちらのセッションでは、トヨクモkintone収穫会アフターイベントにお申し込みいただく際に、皆さんからいただいた質問に回答いただくトークセッションとなっております。
それでは、はじめに今回ご登壇いただくお二人から自己紹介をお願いいたします。
株式会社SBI証券 吉田敬史氏
吉田:株式会社SBI証券 デジタル業務推進部の吉田と申します。SIerを経てSBIに入社し、現在は社内のDX推進に取り組んでいます。
2023年にkintoneとトヨクモ製品を同時に導入し、本日まで約1年間利用しております。
社員数が約900人になりまして、ほぼ全員がFormBridgeやkViewerを利用している状況です。ただし、開発者ではなく、あくまで利用者として使っていただいています。
開発者としては、市民開発者を含めて社員の中で20名ほどが開発に携わっています。トヨクモ製品の管理と開発については、5名ほどで回している体制です。
本日はよろしくお願いします。
株式会社成田デンタル 吉原大騎氏
吉原:株式会社成田デンタル デジタル推進室の吉原と申します。kintone hive 2024 東京では、関東・甲信越地区代表として登壇させていただきました。
営業を6年間経験し、現在は社内のデータ活用を軸にITツールの管理・運用・活用浸透などの業務にあたっています。
社員数は約260人で、全員にkintoneのアカウントを付与してユーザーとして活用いただいています。kintoneの管理者は私1人となっており、構築者は私を含めた3人という体制です。
Xやnoteをやっているので、ぜひフォローしていただけますと幸いです。本日はよろしくお願いします。
アプリ開発の準備と記録の残し方
 トヨクモ:それでは、早速お二人に全部で4つの質問にお答えいただければと思います。
トヨクモ:それでは、早速お二人に全部で4つの質問にお答えいただければと思います。
まず1つ目の質問は、「アプリ開発を始める前の準備、また仕様や経緯の記録の残し方で工夫があれば教えてください」とのことです。吉田さん、いかがでしょうか?
吉田:準備として大事なのは、やはり業務フローですね。ヒアリングして業務フローを作り、ユーザーと話し合うことが重要だと考えています。
これを通して、社員に「業務で何をしているのか理解していますよ、分かって取り組んでますよ」ということをお伝えして、信頼感を醸成することが必要です。
当社は人数が多い会社なので、いきなり「はじめまして!業務改善しましょう」となると、どうしても身構えられてしまいます。
そのため、こちら側が理解していることをお伝えしつつ、一緒に改善していこうということで、業務フローを作って話ながら進めていくということをしていますね。
仕様や経緯の記録の残し方については、実はあまり細かい設計書は残していません。ただ、どうしても記録が必要だと考えているのが、トヨクモ製品でリリースしたものの一覧です。
FormBridgeやkViewerは、1つのkintoneアプリに対して複数設定できるため、見ただけでは本番で使っている設定なのか分からないことがあります。
なので、リリースしたサービスを一覧として管理することだけは必ずしています。
トヨクモ:ありがとうございます。吉原さんはいかがですか?
吉原:準備については、規模が大きくないので、依頼がきたら「やってやろうぜ」というスタンスで取り組んでいます。
ただ、依頼があったときに、その業務について詳しく確認することは意識していますね。
その業務が依頼者個人でやっているものなのか、もしくは全社規模に展開してアプリ構築していけそうなものなのかを、まず最初に確認します。
あとは、依頼内容と同じ業務をやっている人や関係部署にもヒアリングをして、その業務がどこまで影響しているものなのか、範囲をしっかりと調べます。
その上で、こういったパッケージを作りましょうという確認をしていますね。
仕様や経緯の記録については、私がほとんどのアプリを作ることもあって、ほとんど頭の中でやっている状況です。
頭の中でデータの動きを覚えているので、個人であれば特に問題なかったのですが、構築者が増えたときに問題が出てくる可能性はあります。
実は最近の事例がありまして、新しい構築者の人が自身で作ったアプリを見て「このアプリ、どういう動きするんだっけ?」と分からなくなっていたのです。
そうなっているのを見て、やはりユーザー側がどのような形で使うのか、システムがどう動くのかは、マニュアルとして残しておくべきだなと考えるようになりました。
トヨクモ:確かに、全て自分で構築して見慣れていたら特に問題なくても、新しく構築する方やkintoneを見慣れていない人がスムーズに設定や修正ができるようにするか考えるのは大事ですよね。
トヨクモ製品での失敗事例
トヨクモ:それでは、次の質問です。トヨクモ製品の失敗事例があればお聞かせください。まずは、吉原さんからお願いします。
吉原:DataCollectをライトコースで導入してしまったことですね。元々は他の部署が使いたいということで導入したのですが、使わずじまいになっていました。
そこで私が使おうとしたのですが、ライトコースだと自分が使いたかった機能が使えませんでした。なので、導入するときは1つ上のコースで上長に提案して、導入してもらった方が後々いいかもしれません。
もう1つ、PrintCreatorでも最近失敗事例があります。書類で使う背景をExcelで作ってPDFに出力しているのですが、作りすぎてしまいファイルが行方不明になってしまいました。
背景PDFの管理もしっかりしておく必要があるというのが、最近の失敗事例です。
トヨクモ:確かに背景のPDFは皆さまに作っていただくものですし、原本が行方不明になると困りますよね。吉田さんはいかがですか?
吉田:kViewerでありました。ビューを公開したので皆さん使ってくださいと共有したのですが、IPアドレス制限をかけていたので自分のオフィスからしかアクセスできない状態になっていました。
それに気付かずリリースしたので、他部署から「つながらないよ」というクレームがいっぱいきたのが、トヨクモ製品での失敗になりますね。
現場で使ってもらうためのコツ
トヨクモ:次は、1人で設定を担当されている方からのお悩みです。「製品導入から現場浸透までがうまくいかない」ということで、現場で使ってもらうためのコツなどがあれば、ぜひ教えてください。吉田さん、いかがですか?
吉田:2つほど答えがあると思っています。
まず、手が足りないのであれば、外部のSIerの伴走サービスなどを使い、スタートの走り出しのところを助けてもらいつつやっていくというのが1つ。
それができ始めたら、各部署で一人kintoneの開発をやってくれそうな人を選び、kintoneのアカウントを渡して、権限移譲していくのがいいのではないでしょうか。
トヨクモ:どんな人がkintoneの開発をしてくれそうというイメージはありますか?
吉田:やってくれそうな人は、逆に口うるさい人ですね。あえて少し足りていないものを渡してみて、「こういうのが欲しいんだけど」と言ってきたら、「それkintoneでできますよ」と伝えます。
そこから、「管理者権限も与えるので、これでやってみてください」とヘルプのURLなどを渡してみましょう。
当然、「分からない」と返って来ると思うので、「それなら画面共有して一緒にやりましょうか」と巻き込み、無理やり教えてしまうということを私は実際にやっています。
トヨクモ:今の開発者もそのように増やしてこられたのでしょうか?
吉田:そうですね。市民開発者20人中の4〜5人は、そうやって無理やり押し付けつつ育ってもらいました。
トヨクモ:明日から実践できそうなコツだと思います、ありがとうございました。それでは、吉原さんはいかがでしょうか?
吉原:ちょうど今、PrintCreatorでフォーマットを統一するよう進めているのですが、やはり現場と徹底的に会話をしながら広めていく必要があるなと感じています。
なので、まずは現場の業務を理解することから始めてください。
理解できていないなら、実際に現場まで足を運んで、現場の動きや業務内容、社員がどんな気持ちで取り組んでいるかなどをしっかり見て理解することが大切だと思います。
やはり、「このフォーマットに統一しますよ。使ってくださいね。」と言っても、人は動きません。
まずは、なぜ取り組んでいるのか腹落ちさせるのが大事で、その上で使い方などの説明に移るべきなのかなと考えています。
あとは、キーマンを抑えてボトムに落としてもらうという方法も効果的ですね。
例えば、営業所の上長を抑えて、上長からメンバーに落としてもらうという流れです。テストや勉強などでは、自分の言葉で教えた方が理解が深まるじゃないですか。
それを、営業所の上長のようなキーマンにやってもらっていくと、現場にも広まっていくのではないかと思います。
トヨクモ:確かに、全然知らない人から「これ使って」と言われても、急には使えなかったり、反発が出てきたりするかもしれないですね。
DXといえど、まずは泥臭く現場に足を運んで、現場にいる人を知ることが大事だということで、大変参考になりました。
利用規定や教育方法の工夫
トヨクモ:最後の質問になります。トヨクモ製品を社内で使うにあたり、利用規定や教育方法で工夫していることがあれば教えてください。それでは、吉原さんからお願いします。
吉原:まず、利用規定について。kViewerの話になりますが、これらは閲覧制限をかけなければいけない情報を見てもいい立場の人のみが触るべきプロダクトだと認識しているので、使える人を管理者とサブ管理者の2人に限定しています。
次に教育方法については、現在はマニュアルを作るようにしています。
PrintCreatorで文字を大きくするやり方とか、PDFで出力する際のやり方とか、印刷の方法まで、手順書を細かく作って教育しています。
別のツールにまで影響しているのですが、そこまで丸々抑えてマニュアルを作るようにしていますね。やはり、皆さんに使ってほしいという想いがあるので、やるべきことなのかなと思います。
トヨクモ:本当に1から、初見の人でも見たらできるぐらいのレベルで作られているのですね。吉田さんはいかがですか?
吉田:トヨクモ製品の利用規定や教育方法とは少しだけズレるのですが、当社ではkintoneアカウントを申請があった人だけに配るようにしています。
その際、利用者の権限とアプリを作成する権限の2つに分けていて、アプリを作成できる人を絞っています。
それが冒頭お話しした20人になるのですが、その人たちに対してはテストを受けてもらいました。
アプリの作成をしたいと申請が上がってきたら、テストを受けてもらい、合格したら権限を渡すという形です。
利用方法の教育については、覚えておいてほしいものをkViewerのカードビューで一覧にして、社内に展開して共有しています。
トヨクモユーザーへのメッセージ
トヨクモ:それでは最後に、お二人からトヨクモ製品をお使いの皆さんに一言ずつメッセージを頂ければと思います。まずは吉田さん、お願いします。
吉田:それでは、さっき言えなかったありがちな失敗例を共有できればと思います。
kViewerでありそうなことになりますが、ビューを作ってみたあとに、何も考えずに公開したら危ないですよということをお伝えしたいです。
なぜかというと、IP制限にチェックを入れずに右上の「公開」を押してしまうと、そのまま全世界に公開されてしまうからですね。
もちろん、私が失敗したというわけではないですが、セキュリティの部分になるので、皆さんもそこは気をつけていきましょう。
できれば、公開時にデフォルトで制限をつけてもらえるとありがたいです。
トヨクモ:要望としてメモさせていただきます。ありがとうございました。次に、吉原さんお願いします。
吉原:そうですね、PrintCreatorの電子契約が3通から増えないかなという要望などはありつつも、トヨクモ製品は非常に素晴らしいなと思っています。
それで、私がここで今日共有したいのが、トヨクモちゃんへの愛ですね。やはり、トヨクモ製品が好きなので、皆さんにはぜひトヨクモちゃんも好きになって欲しいなと思います。
トヨクモ製品以前に、トヨクモという会社を好きになって欲しいと思いますし、トヨクモちゃんを好きになってLINEスタンプも買って欲しいです。皆さん、よろしくお願いします。
トヨクモ:本当にトヨクモちゃんがお好きということで、宣伝までしていただきありがとうございます。
それでは、本日のトークセッションは以上とさせていただきます。お二人とも、本日はご登壇いただきありがとうございました!