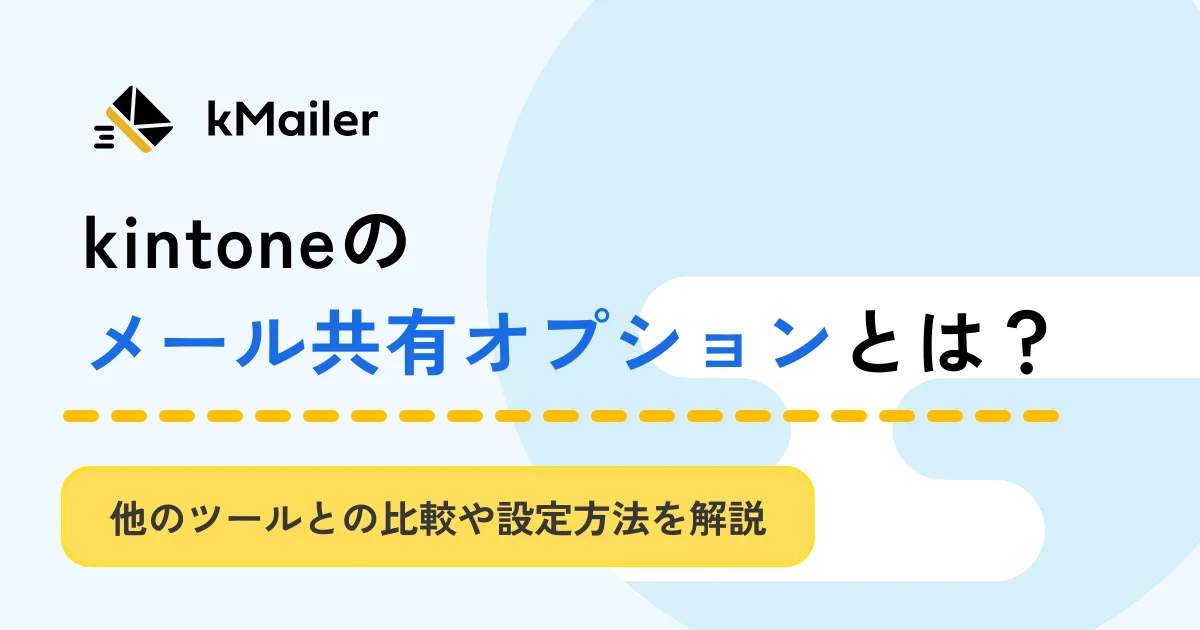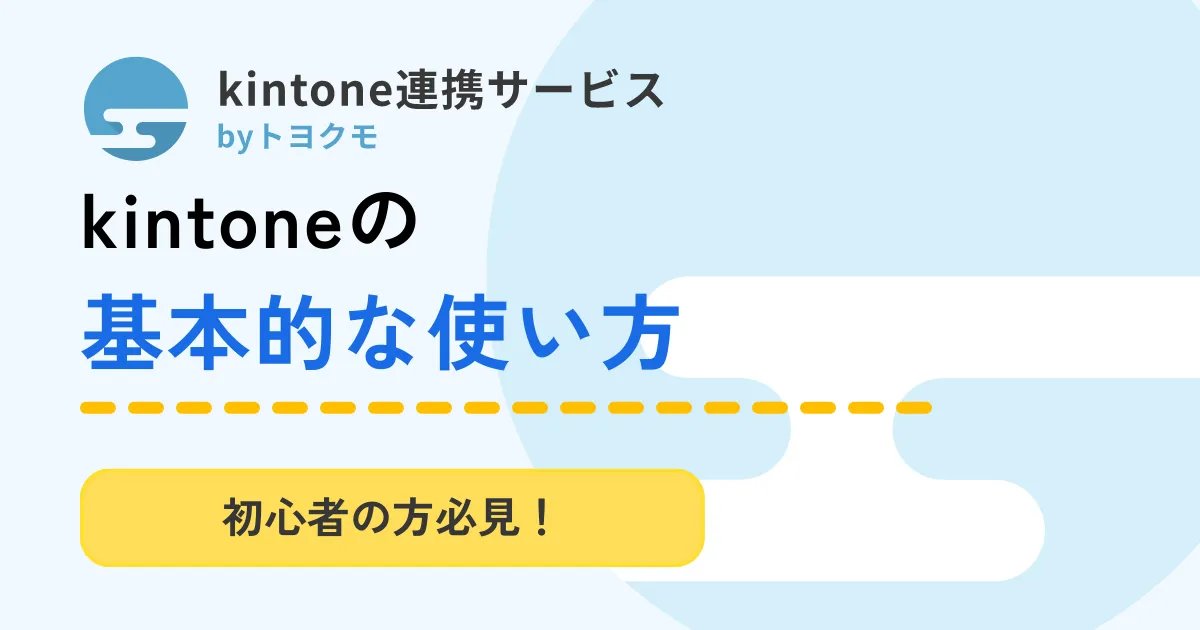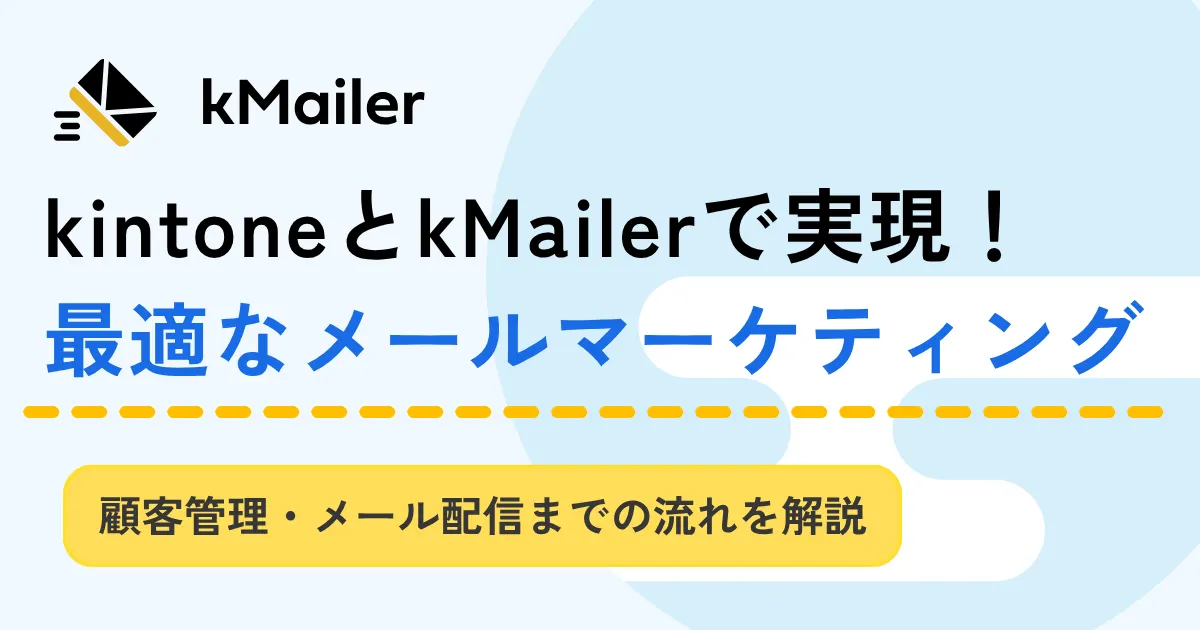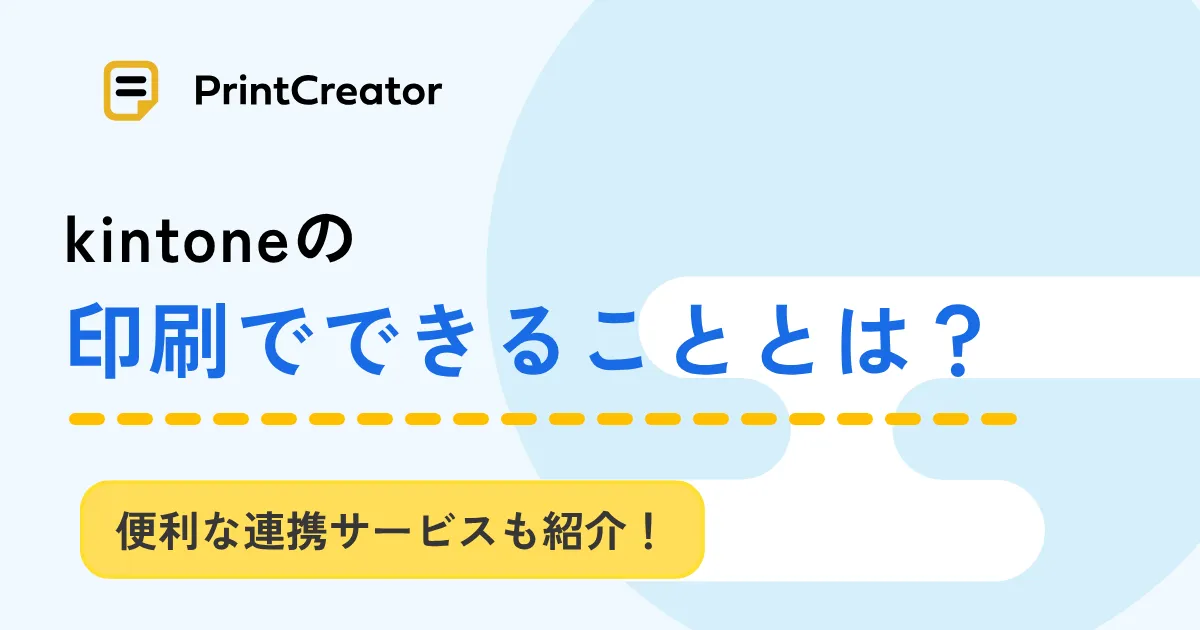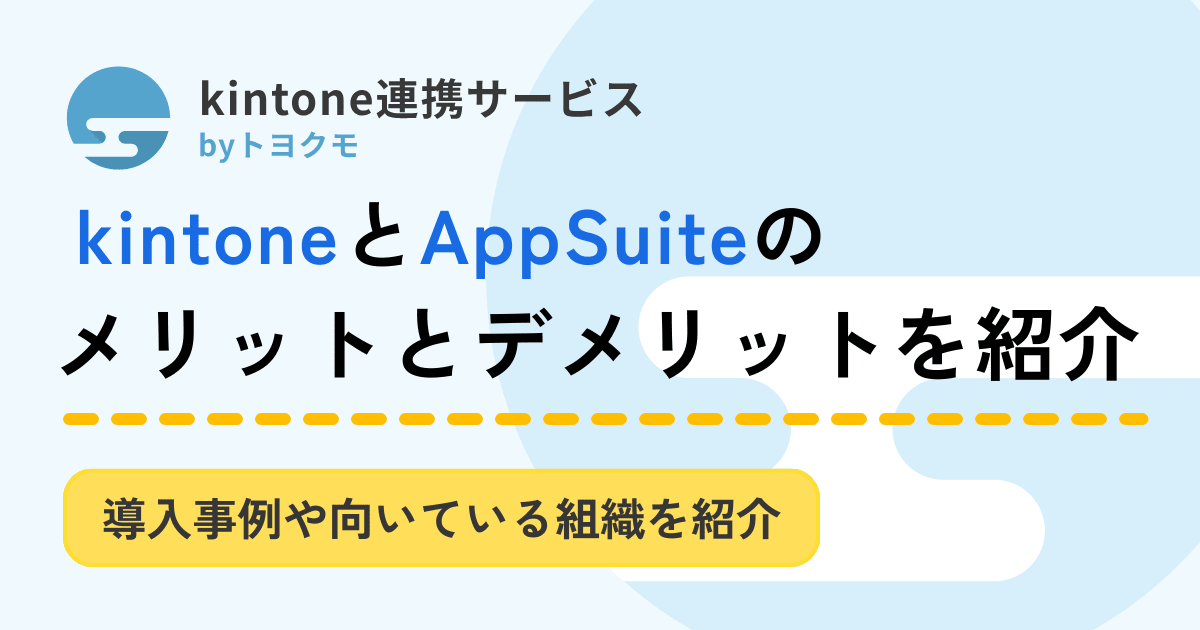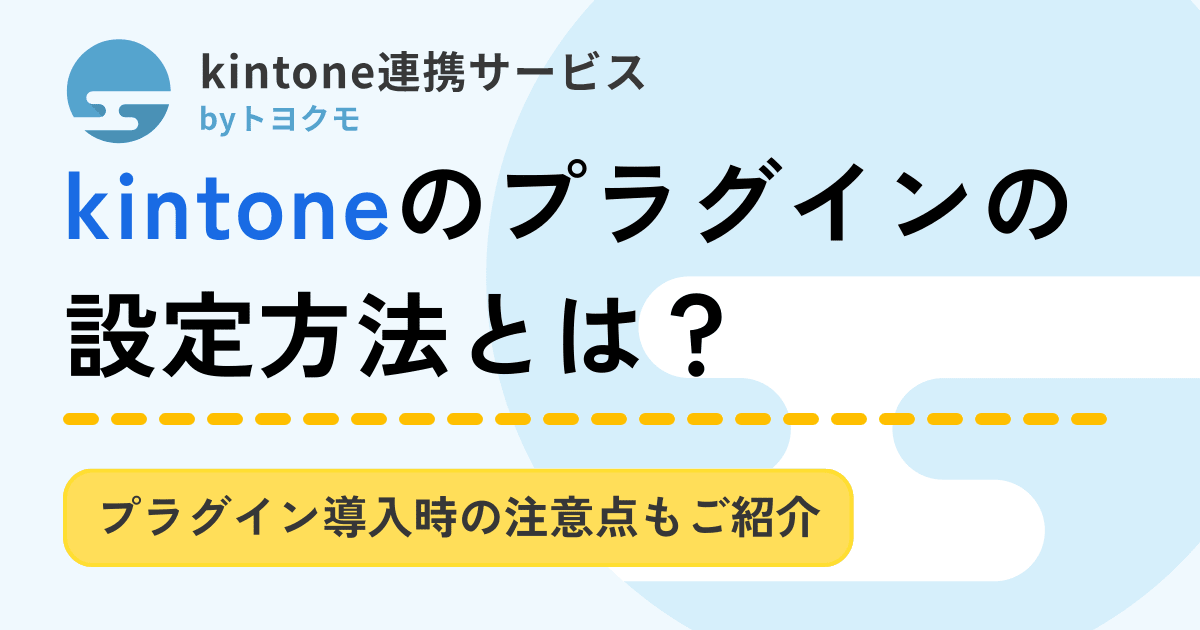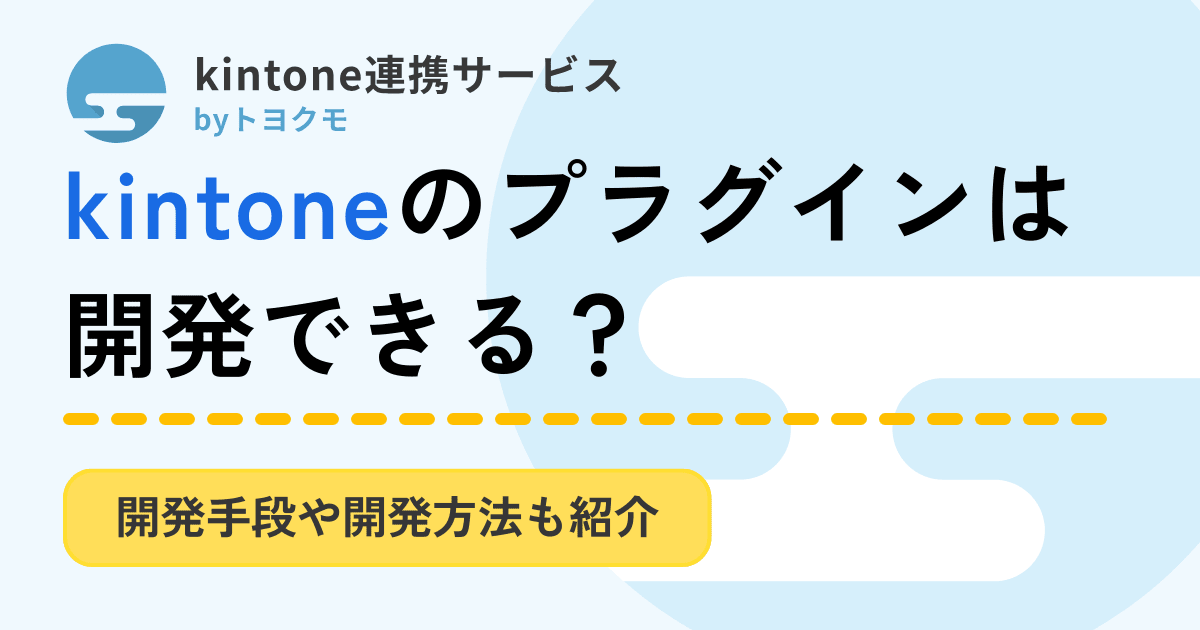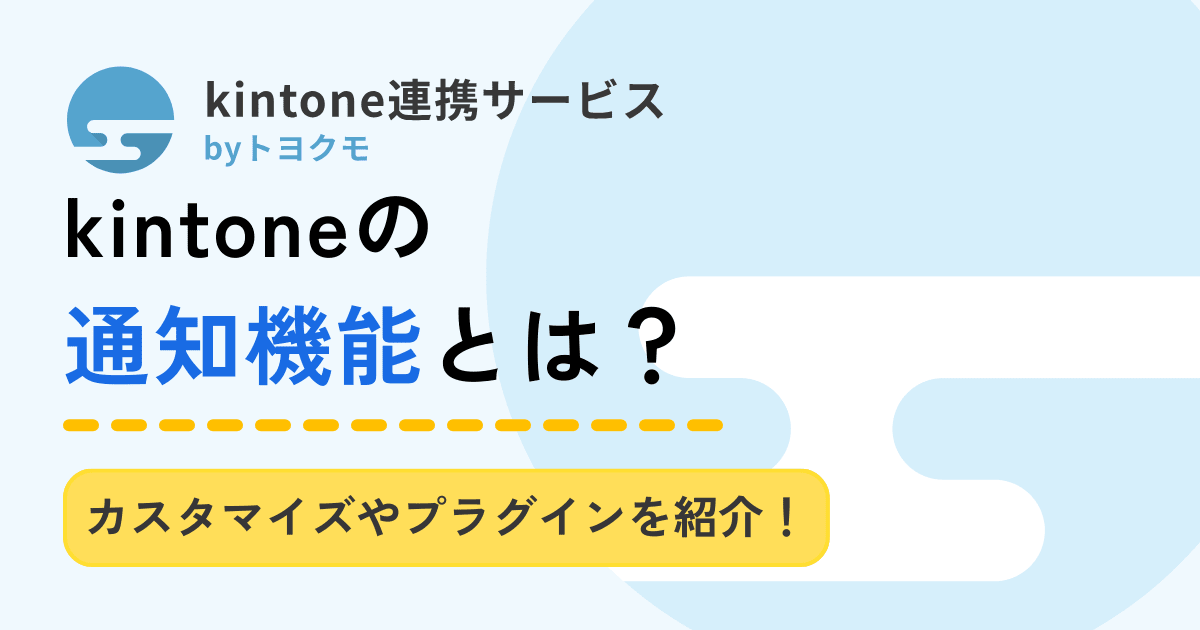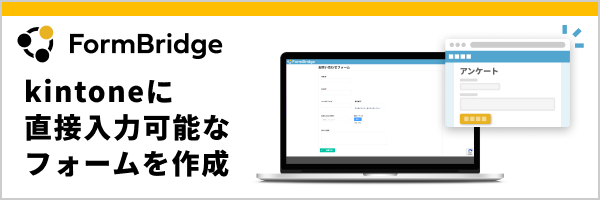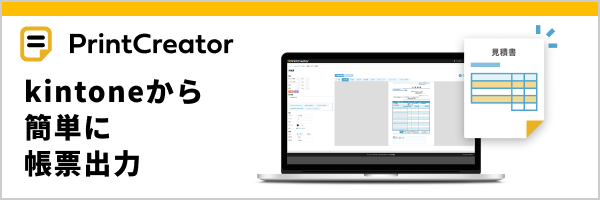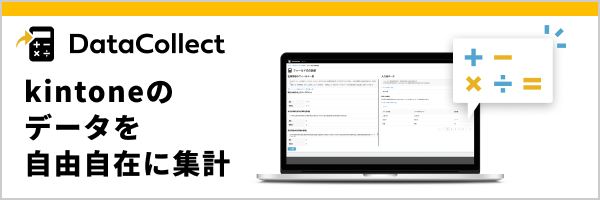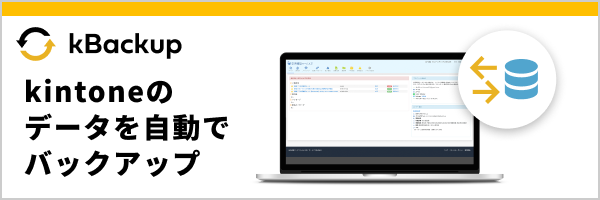kintoneの評判と口コミを分析!導入時活用されなかった事例も紹介

kintoneの導入を検討中の人の中には「kintoneの評判は良さそうだけど、自社に合うか不安」「導入して失敗したくない」と考えている人もいるでしょう。
kintoneは、2026年1月現在、41,000社以上が導入する日本発のノーコードツールですが、すべての企業に適しているとは限りません。本記事では、下記3サイトの口コミ300件以上を参考に、独自の基準を設けてkintoneを総合的に評価しました。
【参考サイト】
- レビュープラットフォーム「ITreview」:アイティクラウド株式会社
- 法人向けIT製品比較サイト「ITトレンド」:株式会社イノベーション
- SaaS比較・口コミサイト「BOXIL」:スマートキャンプ株式会社
目次
kintoneは現場主導で業務改善を進めたい企業に評価されている
【評価の基準】
| ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | 大変満足しているかつ、不満が記載されていない口コミが多くあった |
| ⭐️⭐️⭐️⭐️ | 満足している口コミが多いが、不満を抱える口コミも少数 |
| ⭐️⭐️⭐️ | 満足している・不満がある、という相反する口コミが同数程度 |
| ⭐️⭐️ | 不満を抱える口コミが多く、良いという口コミが少ない |
| ⭐️ | 不満を抱える口コミが非常に多いかつ、良いという口コミが少ない |
【kintoneの総合的な評価】
kintoneは「自社業務に合わせて柔軟に仕組みを整えたい」「コスパ良く効率化を進めたい」と考えている企業と非常に相性の良いサービスです。参考サイトの口コミにおいては、導入効果やセキュリティ面に関して満足している利用者が非常に多いことがわかりました。
一方、使いやすさや機能面で不満のある口コミも一定数見受けられました。アカウント数や導入設計の負担など、企業規模や運用設計によって意見が分かれているようです。
kintone導入後の効果に関する評判や口コミ
【導入効果(業務効率化や情報共有の改善の効果)に対しての評価基準】
| ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | 大変満足しているかつ、不満が記載されていない口コミが多くあった |
| ⭐️⭐️⭐️⭐️ | 満足している口コミが多いが、不満を抱える口コミも少数 |
| ⭐️⭐️⭐️ | 満足している・不満がある、という相反する口コミが同数程度 |
| ⭐️⭐️ | 不満を抱える口コミが多く、良いという口コミが少ない |
| ⭐️ | 不満を抱える口コミが非常に多いかつ、良いという口コミが少ない |
|
総合評価 |
業務効率化や情報共有の改善に、大きな効果を感じている企業が多い |
【満足している点】
| 業務効率化 |
|
| ミスと抜け漏れ防止 |
|
| 他部署や社外との連絡の効率化 |
|
| 組織全体の生産性の向上 |
|
導入効果に関する口コミを総合すると、業務効率化や情報共有の改善に大きな効果を感じている企業が多いことが分かります。「タスクを一元管理でき、チーム内での情報共有がスムーズになった」「問い合わせ対応や請求書作成をExcelからkintoneへ移行し、時短になった」といった声が目立ちました。
Excelやメールを中心に行っていた管理からkintoneへ乗り換えたことで、タスクやデータの一元管理が可能となり、ミスや共有漏れの減少や業務全体のスピードと精度の高まりにつながっているようです。
評判や口コミを分析した結果、kintoneを導入した多くの企業が、利用開始からわずか1ヶ月ほどで業務改善の成果を実感していることがわかりました。kintoneのプログラミング不要でアプリを作成できる点や、短期間で社内の運用体制の整備が可能である点が影響していると考えられるでしょう。
Excelやメール管理からの脱却や、チーム全体で情報の見える化を目指したいと考えている人は、kintoneの活用を検討してみてください。
kintoneのコストパフォーマンスに関する評判や口コミ
【コストパフォーマンスに対しての評価基準】
| ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | 運用コストを大幅に削減できたかつ、不満が記載されていない口コミが多くあった |
| ⭐️⭐️⭐️⭐️ | 運用コストを削減できたという口コミが多くあったが、プラグインや最安のスタンダードプランの限界を感じる声もあった |
| ⭐️⭐️⭐️ | 削減できた・あまり変わらなかった、という相反する口コミが同数程度あった |
| ⭐️⭐️ | 削減できなかったという趣旨の口コミが多くあった |
| ⭐️ | 全く削減できなかった上に、むしろ大幅にコストがかかったという口コミが多くあった |
| 総合評価 |
外注せずに社内でアプリを作成できるため、運用コストをまとめて削減できるという声が多い |
【満足している点】
| 月額料金・初期費用の安さ |
|
| 外注費の削減 | 自社に適したアプリを社内で開発でき、コストを大幅に削減できた |
| 運用コストの削減 | 基本、社内だけで改修でき、継続的な運用コストを抑えられた |
【不満がある点】
| 有料プラグイン・外部ツールによるコスト増 |
|
| 利用人数が増える際の負担 | 規模拡大時のコストが気になった |
kintoneのコストパフォーマンスに関しては、価格と機能のバランスに満足している利用者が多いことが分かりました。初期費用がかからず、社内で自由にアプリの作成や改修ができる点が高く評価されており「結果的にコスト削減につながった」という声が寄せられています。
「他社サービスからkintoneに乗り換えたら月額料金が下がった」「社内でアプリを作れるため、外注費がかからず大幅にコストを抑えられた」といった意見もあり、運用を重ねるほど費用対効果を実感しやすい点が魅力といえます。
一方「プラグインや外部連携を利用する際、追加でコストがかかる」「規模を拡大しユーザー数を増やす際のコストが気になる」と感じる声もありました。
コストパフォーマンスにかかわる評価や口コミを調査した結果、初期費用を抑えつつ、自社に合わせた形で拡張できる柔軟性があると感じている人が多いことがわかりました。自社に合わせてカスタマイズできることから、成長途中の企業も導入しやすいと言えるでしょう。
kintoneの使いやすさに関する評判や口コミ
【使いやすさに対しての評価基準】
| ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | 大変満足しているかつ、不満が記載されていない口コミが多くあった |
| ⭐️⭐️⭐️⭐️ | 満足している声が多数だが、機能が充足しているが故の使用感への不満の口コミも一定数見られた |
| ⭐️⭐️⭐️ | 満足している・不満がある、という相反する口コミが同数程度 |
| ⭐️⭐️ | 十分・使えない、などの不満を抱える声が多くあった |
| ⭐️ | 非常に不十分・非常に使えない、などのクレームに近い口コミが多くあった |
|
総合評価 |
【満足している点】
| 作りやすさ |
|
| 情報管理のしやすさ |
|
| 操作のしやすさ |
|
【不満がある点】
| 導入初期の負担 |
|
| UI・デザイン面の見やすさ | 一目見た時にUIにとっつきにくさを感じる方もいるかもしれないと感じた |
| 慣れるまでの負担 | 多機能な分、導入初期は慣れるまで手間をかかる場合があった |
kintoneはノーコードで直感的に操作でき、誰でも業務アプリを作れる手軽さが高く評価されています。「ある程度のカスタマイズなら自分たちでも簡単に可能」「社内の資料をkintone上にまとめられるのが便利」といった声が多く、専門知識がなくても自社に合ったシステムを構築しやすい点が支持を集めています。
また、スマホアプリの操作性や動作の軽さも好評で「出先でもすぐアクセスできる」「直感的に使える」といった利便性を評価する声も多く見られました。
一方「初期設定に時間がかかる点」や「慣れるまでは操作を煩雑に感じる」「UIを改善してほしい」という意見もあります。
kintoneの使いやすさを調査した結果、kintoneは初心者でも扱いやすく直感的な操作ができる一方、慣れるまでは使いづらさを感じる人もいるということがわかりました。kintone導入時は、日常で使える簡単なアプリから作成し、kintoneに頻繁に触れる機会を作ることが望ましいでしょう。
なお、kintoneの公式サイトには、豊富なマニュアルや参考資料が掲載されています。kintoneを使っる際にわからないことが出てきたら「お悩み相談ナビ」から、自分の状況に合ったメニューやカスタマーサポートを活用してみてください。
kintoneの機能面に関する評判や口コミ
【機能面に対しての評価基準】
| ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | 大変満足しているかつ、不満が記載されていない口コミが多くあった |
| ⭐️⭐️⭐️⭐️ | 満足している声が多数だが、機能が充足しているが故の使用感への不満の口コミも一定数見られた |
| ⭐️⭐️⭐️ | 満足している・不満がある、という相反する口コミが同数程度 |
| ⭐️⭐️ | 十分・使えない、などの不満を抱える声が多くあった |
| ⭐️ | 非常に不十分・非常に使えない、などのクレームに近い口コミが多くあった |
|
総合評価 |
【満足している点】
| カスタマイズ性 |
|
| 業務改善面 |
|
| 情報管理 |
|
【不満がある点】
| 機能が充実しているからこその課題 |
|
| 高度なことを行う時の課題 |
|
kintoneは「自社に合わせて柔軟に業務アプリを作れる自由度の高さ」が大きな強みとして評価されています。テンプレートを活用すれば初期構築もスムーズで、プログラミング知識がなくてもアプリを作成し、運用できる点が好評です。
「プログラムの知識がなくても簡単にアプリを作成でき、業務のペーパーレス化ができた」「必要な仕組みをすぐに社内だけに作って試せるため、短期間で業務改善につなげやすい」といった声があり、スピード感を持って業務改善を進められる点が評価されています。
とくに、取引先数や扱う情報量が多い企業にとっては、現場のアイデアをすぐ反映できる柔軟さが大きな利点となっているようです。複数人で同時に作業してもデータの整合性を保てる安定性があるという声も多く、業務基盤としての信頼性も高い印象がありました。
一方「より細かく自社のスタイルに合わせたり独自の運用を行ったりする場合には、API連携やプログラム知識が必要になるケースがあること」を気になる点として挙げている方もいます。
調査の結果、kintoneは「現場主導で仕組みを作りたい企業」と非常に相性のいいツールであると言えます。なお、kintoneを使うときに、どうしても高度なカスタマイズが必要になった場合は、プログラムの知識がある人やkintoneユーザーのコミュニティである「キンコミ」などを活用して相談してみてください。
kintoneのセキュリティ面に関する評判や口コミ
【セキュリティに対しての評価基準】
| ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | 大変満足しているかつ、不満が記載されていない口コミが多くあった |
| ⭐️⭐️⭐️⭐️ | 満足している口コミが多いが、不満を抱える口コミも少数 |
| ⭐️⭐️⭐️ | 満足している・不満がある、という相反する口コミが同数程度 |
| ⭐️⭐️ | 不満を抱える口コミが多く、良いという口コミが少ない |
| ⭐️ | 不満を抱える口コミが非常に多いかつ、良いという口コミが少ない |
|
総合評価 |
【満足している点】
| 安全性の高い設定 |
|
| セキュリティ性の高い仕様 |
|
セキュリティ面に関する口コミを総合すると、kintoneは「安心して使えるツール」として高く評価されています。アクセス権限の細かな設定や二段階認証、外部ユーザーを安全に招待できるゲストスペース機能など安全性を高める仕組みが整っているのが魅力です。
実際に「アプリ内の項目ごとにアクセス権を設定でき、セキュリティ強化できた」「社外から利用する際に2段階認証があり、安全に使える」など、社内はもちろん社外から利用する際も安心できるという、うれしい声が複数ありました。
セキュリティ基準が厳しい会社も問題なく導入できたという意見もあります。セキュリティ面に関する不満の声は、参考サイトでは見当たらなかったため、kintoneは利用に不安を感じている企業でも安心して導入できる、安全性の高い業務ツールといえるでしょう。
kintoneのサポート体制に関する評判口コミ
【サポート体制に対しての評価基準】
| ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | 大変満足しているかつ、不満が記載されていない口コミが多くあった |
| ⭐️⭐️⭐️⭐️ | 満足している口コミが多いが、不満を抱える口コミも少数 |
| ⭐️⭐️⭐️ | 満足している・不満がある、という相反する口コミが同数程度 |
| ⭐️⭐️ | 不満を抱える口コミが多く、良いという口コミが少ない |
| ⭐️ | 不満を抱える口コミが非常に多いかつ、良いという口コミが少ない |
|
総合評価 |
【満足している点】
| 窓口のサポート品質 |
|
| 質の高いサポート情報と
学習機会の提供 |
|
【不満がある点】
| 情報量やサポートの回数 | 動画や専門書、サポートの回数などが増えるとより活用しやすいと感じた |
| フォローアップ体制 | フォローアップがもう少し充実すると使いやすい
ex)実務での活用例や相談窓口など |
kintoneは「初心者でも安心して使い始められるサポートの充実度」が評価されています。電話やメールでの対応が丁寧で、質問にも翌日には的確な回答がもらえるなど、対応スピードと分かりやすさの両面で満足している声が多く見られました。
実際の口コミでも、「電話サポートが丁寧だった」「初心者向けマニュアルが見やすく、初めてでも安心して使い始められた」といった声が目立っており、初めてkintoneを導入する企業でも安心して運用を始められる体制が整っていることが分かります。
また、オンラインセミナーやWeb記事など、学びの機会が豊富に用意されている点に満足している方の声もありました。
一方、もっとkintoneをうまく活用したいと考えているユーザーからは「学習用の専門書や動画の事例をもっと増やしてほしい」といった要望も見受けられました。
kintoneのサポート体制の評判や口コミは、基本的なサポートの質に満足している利用者がほとんどでした。kintoneの事例や参考資料、カスタマーサポートの窓口はkintonel公式サイト「お悩み相談ナビ」から確認できます。
kintone導入当初に活用されなかった失敗を含む事例
kintoneを導入する際、どのような環境であると活用されないのか、事例をもとに紹介します。本記事で紹介する事例は、導入当初に社内では活用されなかったkintoneが、担当者の工夫により社内に定着して業務効率化に繋がった事例です。
【kintone導入当初に活用されなかった事例】
- 現場の人間がkintoneアプリを作る仕組みが必要だった事例
- 担当者の退職によりkintoneアプリが煩雑化した事例
- kintone導入チームと現場の温度差が課題だった事例
- kintone導入推進担当者の啓蒙活動がカギとなった事例
- 社員の抵抗感が強くkintoneの活用が進まなかった事例
現場の人間がkintoneアプリを作る仕組みが必要だった事例
空き家のリフォームやワンルームマンションの施工などの建築・建設に関わる業務を請け負っている株式会社後藤組は、アナログな現場をデジタル化するため、担当者がアプリを作成していました。しかし、現場でアプリは使われず、現場のメンバーとは話が噛み合わなくなってしまいました。
【現場の人間がkintoneアプリを作る仕組みが必要だった事例】
| 失敗例 |
|
| 工夫したこと |
|
| 使ったツール | kintone |
| 成果 |
|
参考:kintone公式サイト「事例|後藤組 様の導入事例」
あるとき、社長から現場の人間が自らアプリを作る仕組みを作るよう依頼され、kintoneの有用性を知ってもらうステップが必要だったことに気づいた担当者は、シンプルな日報アプリを作成しました。1つの部門から簡単なアプリを使ってもらったことで、良い反響をもらえたのです。
その後、日報アプリは全社に定着し、全社員が利用するほかの申請業務もすべてkintoneに載せ替えることで、全社員が1日1回はkintoneに触れる土壌を作り上げました。
社内では、kintoneアプリの勉強会やワークショップを開催するなどの工夫をして、アプリを作成して使ってもらう機会を増やしました。その結果、紙や電話、FAXで行なっていた建設現場がほぼ電子化に成功しました。
kintone導入から1年6ヶ月で、社員の総残業時間は20%減少し、営業利益は44%増加しました。シンプルで簡単なkintoneアプリを1部門から導入し、生産性の大幅な向上につながった事例です。
担当者の退職によりkintoneアプリが煩雑化した事例
日本全国の「あそび」を紹介しているサイト「asoview!(アソビュー)」を運営しているアソビュー株式会社では、kintone導入当初に指揮をとっていた担当者が退職してから、kintoneが活用されなくなっていました。管理者のいないkintoneは無法地帯となっており、業務に有用なシステムに復活させる必要がありました。
【担当者の退職によりkintoneアプリが煩雑化した事例】
| 失敗例 |
|
| 工夫したこと |
|
| 使ったツール | kintone |
| 成果 |
|
参考:kintone公式サイト「事例|アソビュー 様の導入事例
再度kintoneを現場で使ってもらうために、担当者はkintoneについての理解を深め、現場の業務の流れに沿ったアプリを設計しました。現場の業務の目的にこだわった設計を行ったことで、アプリの使い方の説明をしていないにもかかわらず、サポート部門の生産性を2.9倍向上させることに成功したのです。
また、入力時のストレスを最小限にした設計にすることで、kintoneへの入力を現場の人に徹底してもらうことができ、全社にkintoneが定着していきました。業務の流れに合ったシステムに生まれ変わらせたことで、kintoneの活用が成功した事例です。
kintone導入チームと現場の温度差が課題だった事例
営業と製造現場の情報共有が課題だった有限会社光成工業は、kintone導入チームを発足したものの、日報の入力率は18%にとどまっていました。活用が進まない原因は、会社全体で「紙の完全廃止」を行う覚悟を見せていないからと結論づけ、情報共有のための動画作成やキックオフイベントを開催しました。
【kintone導入チームと現場の温度差が課題だった事例】
| 失敗例 |
|
| 工夫したこと |
|
| 使ったツール | kintone |
| 成果 |
|
参考:kintone公式サイト「事例|光成工業 様の導入事例」
動画による共有やキックオフイベント後には、日報の入力率は81%にまで増加し、ほかの社員たちがkintoneを使ったイベントを開催したことで全社にkintoneの活用が広まっていきました。結果、課題であった営業と製造現場の情報共有にkintoneを活用し、受注表の一本化に成功したのです。
情報伝達のミスがなくなり、営業と製造現場の関係性の改善にもつながりました。kintoneの導入の際、しっかりと社内への周知や宣言を行うことで、全社に浸透した事例です。
kintone導入推進担当者の啓蒙活動がカギとなった事例
靴の小売を中心とした事業を展開し、オーダーメイドのインソールを提供している有限会社中山靴店は、利便性の高いアプリを作成するも、kintoneの活用が広がりませんでした。導入推進担当者が1人アプリ作成に奮闘するも、使ってもらえず社員は離職していく状況でした。
【kintone導入推進担当者の啓蒙活動がカギとなった事例】
| 失敗例 | ・無料のプラグインやネット上の情報を調査し、アプリを作成
・さまざまな利便性の高いアプリを作成するも、活用が進まない |
| 工夫したこと | ・東京で開催されていたCybozu Days 2018に参加
・サイボウズの社員に相談 ・社内でkintoneのハンズオンセミナーを開催 ・社内の啓蒙活動に力を入れる |
| 使ったツール | kintone |
| 成果 | ・社内でkintoneアプリを作成する人が現れる
・kintoneを通じたコミュニケーションが増え、データが集まる ・日報にほかの社員からいいねやコメントがつことでモチベーションにつながる |
参考:kintone公式サイト「事例|中山靴店 様の導入事例」
サイボウズの社員の方に相談をし、現場に使ってもらうよう啓蒙活動を地道に続けていくことが必要であると気づいた導入推進担当者は、社内でハンズオンセミナーを開催しました。
現場の人にkintoneの有用性を説く活動をすることで、徐々にkintoneを通じたコミュニケーションが増え、日報アプリも活用されていきました。
今では、kintoneで行う報告に対しての「社員のいいねやコメント」がモチベーションにつながっているそうです。導入推進担当者が社内でkintoneの啓蒙活動を行った末に、働き方に寄り添った使い方ができた事例です。
社員の抵抗感が強くkintoneの活用が進まなかった事例
空調工事や住宅設備機器工事、ガス工事などの多様な工事を行なっている設備工事事業者の株式会社ミヨシテックは、顧客管理システムのクラウド化のためkintoneを導入しました。しかし、これまでのシステムと見た目が異なることから社員から強い抵抗やクレームに見舞われていました。
【社員の抵抗感が強くkintoneの活用が進まなかった事例】
| 失敗例 |
|
| 工夫したこと |
|
| 使ったツール |
|
| 成果 |
|
参考:kintone公式サイト「事例|ミヨシテック 様の導入事例」
kintoneの導入担当者は、度重なるシステム変更による社員の抵抗をなくすため「Chatwork」を継続利用することにしました。また、kintoneに慣れてもらうために毎日使える簡単なアプリである「ゴミ回収記入アプリ」を作成しました。
実際のゴミの量とアプリに入力された量の差を可視化できる「ゴミ回収管理アプリ」も作成しました。プラグインを使って実際のゴミの量との差異を算出し、Chatworkで共有するようにしたことで、コミュニケーションの無駄がなくなったのです。
電話受付業務でもアプリと電話入電システムを導入し、連絡先の登録や対応状況の更新がスムーズになりました。結果、kintoneへの情報集約が進み、経営上の必要な情報を可視化することに成功しました。
今では、システム課以外の部署でもアプリ作成が可能となりました。慣れたツールを残し、社員の抵抗を弱めて簡単なアプリから導入したことで、全社に定着した事例です。
kintoneを導入する際の注意点
kintoneを導入する際は、口コミの不満や事例の失敗例などを参考に、注意点を確認しておきましょう。
【kintoneを導入する際の注意点】
| 導入時 |
|
| コスト |
|
| 操作性 |
|
| 機能 |
|
| セキュリティ | プラグインやkintone連携サービスはkintone公式で紹介されているものを選ぶ |
| サポート体制 |
|
たとえば、kintone導入時は「導入目的と運用範囲」を明確にしましょう。「どの業務を効率化したいのか」を決め、小規模で導入することで、課題が見えやすくなります。また、現場の声を反映しながら改善することで、業務にあったアプリが効率的に作成できます。
コストパフォーマンスを考慮する場合は、kintoneの基本機能や無料プラグインで代用できないか確認しましょう。必要な機能をリストアップし、機能にあったプラグインを探すことで余計なコストを抑えられます。
また、kintoneは10ユーザー単位の申し込みが必要なツールです。1人当たりのコストを抑えるなら10名以上のチームで利用することが望ましいでしょう。
なお、無料プラグインは「kintoneの無料プラグイン一覧|用途別のおすすめを紹介」で紹介しています。プラグインや連携サービスを選ぶ際は、kintone公式サイトで紹介されているものであれば「kintone 連携サービス認定基準」を満たしており、セキュリティ上の配慮がされているため安心です。
迷ったらkintoneの30日間無料お試しで実際に使ってみよう!
kintoneの導入に迷っている場合は、「30日間無料お試し」で実際に使ってみることをおすすめします。なぜなら、kintoneは「自社の業務に合うかどうか」を触ってみて初めてわかる部分が多いからです。
アプリの作り方や操作のしやすさ、連携のスムーズさなどは、文章や口コミを見るだけでは判断がつきません。無料お試し期間では、実際に使いたいアプリを作ったり、チームで共有したりと、本番とほぼ同じ環境で検証できます。
「どこまで内製できるか」「現場メンバーに定着しそうか」も、この期間でしっかり確認できます。導入前の評判や口コミには、導入の判断のしやすさやサポートの手厚さなどの評価がなされていました。
【導入前の評判や口コミ】
| 導入前の判断のしやすさ |
|
| 導入相談の手厚さ |
|
導入後のギャップをなくすためにも、まずは30日間の無料お試しを使ってみて、自社で活用できそうかどうか確かめてみてください。
また、kintoneの導入が成功した事例を「kintoneの活用事例を業種別に紹介!自社に合う活用方法を見つけよう」で紹介しています。具体的な導入効果や変化を参考にしたい人は、ぜひご覧ください。
まとめ
kintoneは、現場主導で柔軟な業務改善を進めたい企業にとって、非常に満足度の高いツールです。プログラミング不要でアプリを自作できるため、導入から短期間で業務効率化や情報共有の改善を実感できます。
多くの企業がExcelからの移行やコスト削減に成功していますが、現場との温度差や運用設計の不足により、活用が進まない事例も存在します。導入を成功させるには、まず小規模な範囲からkintoneの運用を開始し、現場の声を取り入れながら改善を繰り返すことが重要です。
自社に適しているか判断するために、まずは導入目的を明確にした上で「30日間の無料お試し」を活用してみてください。実際に操作することで「基本機能でどこまで内製化できるか」や「現場のメンバーに定着しそうか」などを具体的に検証できます。
なお、セキュリティ上の基準を満たしたkintoneの公式認定サービスを選ぶなら、実績と使いやすさに定評がある、トヨクモのkintone連携サービスを使ってみてください。トヨクモのkintone連携サービスであれば、手軽かつ安全にkintoneの機能の拡張が可能です。
まずは「30日間の無料お試し」から始めてみてください。
【トヨクモ株式会社のkintone連携サービス】
| 連携サービス名 | できること |
| FormBridge | kintoneへデータが自動で保存されていくwebフォームを作成できる |
| PrintCreator | kintoneアプリのデータをPDFで出力できる |
| kViewer | kintoneライセンスがない人に、kintoneアプリのデータを共有できる |
| kMailer | kintoneアプリのデータを引用してメール送信できる |
| DataCollect | 複数のkintoneアプリに登録されたデータを集計できる |
| kBackup | kintoneアプリに登録されたデータを安全にバックアップする |